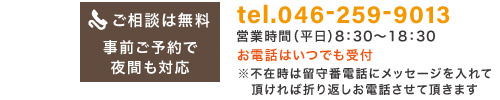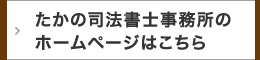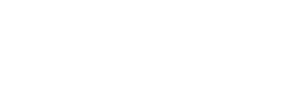Archive for the ‘コラム’ Category
遺言書の検認の必要性について簡単解説
自筆の遺言書は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きを経ないと、各種の相続手続きに使うことができません。
今回はそんな、遺言書の検認について簡単にご紹介します。
■遺言書の検認について
遺言書の検認とは、遺言書の発見者や保管者が、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人の立会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することです。
すべての遺言書に検認が必要な訳ではありません。自筆証書遺言と秘密証書遺言に必要な手続きです。
遺言公正証書は検認手続きを経ることなく、すぐに相続手続きで使用できます。
■遺言書の検認をする目的
遺言書の検認は、相続人に対して、遺言の存在およびその内容を知らせるとともに以下の内容を確認する意味があります。
・遺言書の形状や加除訂正の状態
・日付、署名
検認日時点での遺言内容を明確にし、偽造や変造をされていないか確認し、それ以降の変造を防止するための手続きとして必要なものとされています。
あくまで確認と変造の防止が目的のため、遺言内容の法的有効性を判断する手続きではありません。
■検認の必要性
遺言書の検認手続きをせずに遺言内容を実行した場合は5万円以下の過料が科せられます。封印された遺言書を検認手続き前に開封したときも同様です。
ただそもそも、不動産登記手続きでも、預貯金や株などの相続手続きでも、検認済みの遺言書でなければ使用できません。
遺言書の検認手続きには、様々な必要書類があり、費用もかかります。
不安な場合は、司法書士に相談してみてください。
相続登記をするべき理由について
相続登記を放置すると、相続した資産を失ってしまうかもしれません。
そのようなことがないように、正しい知識をつけておく必要があります。
そこで今回は、相続登記についてご紹介します。
■相続登記について
相続登記とは、簡潔に言うと、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を、相続人に書き換える作業をいいます。
■相続登記の期限
相続登記に期限はありません。相続登記は義務ではなく権利だからです。
相続登記をしないことで発生するデメリットについては以下に解説します。
■相続登記(そのための遺産分割協議)をしないデメリット
・相続人が増えて遺産分割が困難になる可能性
名義人が亡くなってから、相続人に名義を変えるまでは、不動産は相続人全員の共有状態になります。そして、相続人の一人さらに亡くなると、相続人の相続人にまで共有されるのです。
登記するには相続人全員の合意に基づく遺産分割協議書が必要なため、相続人の人数が増えると、なかなか合意に至らず登記することが難しくなる可能性もでてきます。
・認知症による影響
相続登記を放置している間に、相続人の一人が認知症などで判断能力が低下してしまうと、家庭裁判所に申し立てて後見人を選任しなければ、遺産分割協議をすることができなくなります。
・連絡がつかない者が出た場合
相続登記を放置している間に、相続人の一人の行方が分からなくなり音信不通となった場合、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらうなど、面倒な手続きが必要となります。
■相続登記の方法
相続登記の申請は法務局で行います。不動産所在地を管轄する法務局に申請します。登記手続きはご自分でもできます。
ただ、書類に不備がある場合など、何度か法務局に出向かないといけなくなります。
なかなか平日に時間が取れない、面倒なことは避けたいという場合には、司法書士に依頼した方が良いでしょう。
無効にならない遺言書の作成方法について簡単解説
遺言書は誰でも簡単に書くことができますが、ルールに則って書かないと無効になってしまいます。
そこで今回は、無効にならない遺言の作成方法についてご紹介します。
■正しい自筆証書遺言の書き方
自筆証書遺言の書き方は簡単ですが、法律に定められた要件や形式が存在し、それぞれの要件や形式を満たす必要があります。
要件や形式に不備があるがために自筆証書遺言が無効になってしまう事例は結構あります。
そうなってしまうと、自分の思い通りに遺言が執行されなくなってしまいます。
そのため、不安要素がある場合は司法書士などのプロに相談するようにしましょう。
■自筆証書遺言書を作成する上での最低限のルールについて
・遺言の内容、日付、遺言者の署名を全て自書する
パソコンに打ち込んだ物や、代筆してもらったものは無効です。また、音声、ビデオによるのも無効です。
・日付を明記する
作成日を正確に明記してください。確認できない場合無効となります。また、スタンプも無効です。
・署名・押印する
氏名だけで可ですが、住所も書いた方が良いと思います。
また、押印は認印で可ですが、確かに本人が書いた証明として、実印を用いた方が良いと思います。
・加除訂正はルール通りにする
書き間違いの訂正や追加する場合は法律が定めた方式があり、守らないと無効となります。
訂正や追加がある場合は、全て書き直すのが無難です。
・その他の注意点
「遺言の記載内容は具体的に書くこと」
「不動産は登記簿謄本通りに記載した方が良いこと」
「預貯金は金融機関の支店名、預貯金の種類や口座番号まで記載すること」などがあります。
詳細まで記載するようにしましょう。
遺言書が効力を持つのは書かれた方が亡くなってからなので、手違いがあっても正すことができません。
きっちりとルールに従って書くようにしてください。
最も用いられる遺言方法「普通方式遺言」について解説
遺言は法律によって普通方式の3種類、もしくは特別方式の2種類のいずれかを用いて作成することが定められています。
そのため、しっかりとルールに則った方式で遺言を書かなければ無効になってしまいます。
そこで、今回は通常の遺言作成でよく用いられる「普通方式遺言」の3種類についてご紹介します。
■普通方式遺言について
遺言には、大きく分けると普通方式の遺言と、特別方式の遺言の2つの方式があります。
ここでは、普通方式遺言の3つの種類についてご紹介します。
■自筆証書遺言について
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を明記し、押印して作成する遺言形式です。
筆記具と紙さえあればいつでも作成が可能ですので、他の方式と比べて費用がかからず手続きも簡単に行うことができます。
また、自分一人で作成ができますので遺言内容を他人に秘密にすることができます。
しかし一方で、内容を専門家にチェックしてもらうことがありませんので、法的要件不備のために無効となるリスクが存在します。
さらに、紛失や偽造、隠匿の心配や遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題も挙げられます。
■公正証書遺言について
公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管する遺言方式です。
作成に専門家である公証人が関わるため、法的に最も安全・確実な方法といえ、後日の紛争防止のためにも最もおすすめできる選択肢です。
その分費用がかかりますが、将来の相続手続きの際にも、自筆証書遺言のように家庭裁判所での検認手続きが不要で、受遺者にとって手続きが楽にできるというメリットがあります。
■秘密証書遺言について
遺言者が作成した遺言書に自署・押印した上で封印し、公証役場に持ち込み公証人および証人立会いのもとでさらに公証役場の封筒に入れて封印します。
遺言内容を誰にも知られずに済み、偽造防止にもなります。
しかし、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけにはいかないので不備があれば無効になってしまいます。また、費用もかかります。
遺言書に法的な不備があったり、表現が足りないことで相続人同士のトラブルにつながったりすると、遺言の執行が難しくなります。
そのため、遺言に関する知識をしっかりとつけた上で方式を選ぶようにしてください。
遺言書の作成には色々な方法がありますが、それぞれメリット・デメリットが存在します。
後々のトラブルを避けるためにもご自身・ご家族の望む遺言方式で書かれることをおすすめしますので是非参考にしてください。
遺言作成にあたって司法書士に相談するメリット
遺言は法律の専門家に頼まなければいけないという決まりはありません。
法律に定められたルール通りに書けば有効な遺言書を残すことができます。
そのため、ご自分で遺言書を書かれる方もいらっしゃいます。
しかし、それが思わぬ形でトラブルを引き起こしてしまうケースもあります。
そのため、今回は司法書士のような法律の専門家に依頼するメリットについてご紹介します。
■無効にならない遺言書が書ける
遺言書を書いても、法的に無効と判断されれば意味がありません。
そのため、司法書士など専門家に相談して遺言書を書くようにすれば、無効な遺言になってしまうリスクを避けることができます。
また、無効にならなくても正しい表現ができておらず複数の解釈が可能になると、後々トラブルを引き起こしてしまいます。
ご自分で書いた遺言書が本当に、望んでいる通りの結果を得られるのかプ司法書士など専門家に相談すれば正しい法的効果を生じる遺言文案を教えてもらえます。
■しっかりと遺言執行できる遺言書が書ける
遺言書は書くだけでなく、財産の相続手続きができていなければなりません。
法律手続きができてはじめて遺言書が意味をなします。
遺言執行がしっかりとできる内容の遺言書になっているか相談しておくことをおすすめします。
■遺言書作成の文案を作ってもらえる
司法書士など専門家に遺言書の相談をしても、自筆証書遺言を書くのはご自分です。
しかし、文案は司法書士など専門家が提案してくれます。その内容に納得がいけば、あとはご自分の手書きでそのまま転記すれば遺言書が完成します。
■色々な相談ができる
遺言書の作成だけでなく、他の法律問題や法的手続きも相談することができます。
例えば、不動産などの生前贈与や、認知症に備えて任意後見契約の締結、死後事務委任契約の依頼などです。
司法書士は遺言書の作成以外にも色々な日常生活の問題を取り扱っているため、日頃の疑問も相談できます。
司法書士など専門家は必要であれば遺言書の保管もしてくれます。
また、遺言書を書いた後でも、何か法律関連で困ったことがあれば相談に乗ってくれます。
ルール通りに記載されていない遺言書は意味を持たないため、相続人の間でトラブルを引き起こします。
そのため、費用はかかりますが、安全に法的効力のある遺言書を作成するためにも是非、司法書士など専門家に相談してみてください。
相続手続きの流れと基礎知識について簡単解説
相続をすることは一生にそう何度もある事ではありません。いざ相続をする段階になって、どうすれば良いのかわからないというのが実情です。
相続の手続きには期限が決められているものもありますので、相続手続きをおおまかにでも理解しておくと慌てなくても済みます。
そこで今回は、相続手続きの流れについてご紹介します。
■遺言の確認
どの相続人がどの財産を相続するかは、第1に、遺言があればそれに従います。遺言には、「自筆証書遺言」の他、公証役場で作成する「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」などがあります。
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所にて「検認手続き」が必要になります。
■相続人の確定
遺言が無い場合、第2に、相続人全員の協議で決めます。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ有効にならないため、まずは戸籍・除籍・改製原戸籍を取り寄せて、相続人を確定させる必要があります。
亡くなった方が、過去に離婚をしていた場合、前妻との間に子がいたり、養子縁組をしていたりという事もあります。このような場合に、身内も知らなかったというケースも実際にありますので、戸籍をしっかり調査した上で遺産分割協議を行いましょう。
■相続放棄と限定承認
相続放棄とは、すべての遺産の相続を放棄することで、明らかにマイナス財産の方が多い場合に有用です。限定承認とは、マイナスの遺産をプラスの財産内で受け取る手続きで、マイナスとプラスのどちらが多いか明らかでない場合に有用です。いずれも、相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議に関して特にルールはありませんので、全員が同意する内容であればどのような方法で決めても問題はありません。
決定後は遺産分割協議書を作成し、全員の実印を押印して、印鑑証明書を添付します。これが各種の相続手続きで必要になります。
■準確定申告
亡くなった方が自営業者だった場合や、医療費控除を受ける場合には、準確定申告が必要になります。相続開始時から4カ月という期限があります。
■名義変更など
どの相続人がどの財産を相続するか決まったら、不動産や車、株などの名義変更手続き、預貯金の払戻し手続きが必要になります。
また、不動産を相続した場合は早めに相続登記をしておきましょう。
なお、遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続開始時から10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。基礎控除内であれば、申告の必要もありません。
相続放棄のメリット・デメリットについて
遺産の相続は時として、大きな負債を引き継いでしまう可能性もあります。
そこで今回は、相続放棄についてご紹介します。
■相続放棄とは
相続放棄とは、一切の遺産相続をせずにすべて放棄することです。
基本的に誰かが亡くなり相続が開始すると、法定相続人が遺産を承継(相続)します。
遺産としては、現金や預貯金、不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれます。
預貯金などプラスの相続財産で借金が支払いきれない場合は、相続人が被相続人の借金を支払わなければなりません。
相続債権者から催促状が届き、その支払いを放置していると、相続債権者から裁判を起こされ、相続人自身の財産まで差し押さえられる危険もあります。
そのため、明らかに負債の方が多いという場合、特にどうしても引き継ぎたい財産があるという事も無ければ、相続放棄をしておく必要があるでしょう。
■相続放棄の撤回に関して
相続放棄には3ヶ月間の期間がありますが、一度手続きすると、期間内であっても取り消しができません。詐欺によって放棄させられたといった特別の事情があれば取消しできる場合もありますが、基本的にはできません。
■相続放棄のメリット
・負債を相続しないでよい
上記の通り、借金などの負債、未払いの家賃などを相続しないで済みます。
・遺産分割手続きに関わらずに済む
法定相続人になる場合、さまざまな遺産分割手続きを進める必要があります。まずは相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、親族の関係性によっては、何も要らないから関わりたくないという方もいらっしゃるでしょう。その様な場合、相続放棄をすることで、遺産相続手続きに関わらなくても良くなります。
■相続放棄のデメリット
・プラスの遺産も相続できない
負債だけを相続放棄するという事はできません。相続放棄するとすべての遺産を受け取れなくなります。何の調査もせずに相続放棄をした後に、少し調査してみると、負債を大きく超える預金や不動産が見つかったという事もありえます。
相続放棄できる期間は、相続開始を知った時から3ヶ月です。それまでに充分な調査をせずに相続するかどうか決断してしまうと後悔することにもなりかねませんのでご注意下さい。
また、プラスになる資産のみを受け取る限定承認などの制度もありますので、遺産の相続は専門家に相談するようにしてください。
遺言として法的に有効な方法は3種類あります
ご高齢になる、あるいは病気をお持ちになることでご自身が亡くなった時のことについて考えるようになる方もいらっしゃることでしょう。
その時に気になることのひとつは、ご自身の遺産のことかと思います。
「特定の子供に自宅など相続させたい」、「分配はこのようにしたい」などとそれぞれの方が異なった思いをお持ちのことでしょう。
しかし、どんな方でも、自分の資産の相続をめぐって大切な親族が争うことは望まないことと思います。
そこで、争いを未然に防ぐためにも遺言を作成することをお勧めいたします。
遺言(ゆいごん・いごん)とは、人が自分の死後にその効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく意思表示のことです。
このうち、後見人の指定・相続人の選択・資産の分配、といった点は法的効果を生じます。遺言を作成することによってご自身が亡くなった後の相続や資産の配分を揉め事なく行うことが可能になります。
その遺言の方法にはどのようなものがあるのかについてみていきましょう。
◎遺言の3つの方法
遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方法があります。
「自筆証書遺言」は、自分一人で作成するものであり、証人を必要としません。
そのため、内容を秘密にすることが可能です。
作成後は自分で保管します。費用はかかりませんが、遺言内容を執行するには家庭裁判所の検認を経ることが必要になります。
「公正証書遺言」は、遺言を公正証書にして公証役場で作成し、作成後は原本を公証人・正本および謄本を自分自身が保管します。2人の証人が必要ですが、身近に適切な方がいない場合は、公証役場で紹介してもらえます。
費用としては、公証人へ財産価額に応じた手数料と、2人の証人への謝礼金が必要になります。
家庭裁判所の検認は必要ありません。公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成しますので、確実な遺言書が作成できます。
「秘密証書遺言」は、封印した遺言書をさらに公証役場で封印し、作成後は自分で保管します。
こちらも、公証人への手数料と証人への謝礼金が必要です。
遺言内容は公証人に知られない方法ですので、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用できます。
開封時には家庭裁判所の検認が必要になります。
親族に迷惑かけたくない・揉め事の解決をしたいという思いをお持ちの方は多くいらっしゃることでしょう。
遺言を残しておくことは、ご自身の意思を反映するだけではなく、後々も仲の良い親族関係を構築する手助けにもなります。
遺言の作成において注意すべき書き方と費用
今回は遺言の作成において注意すべきこととして、書き方と費用の二つの面でお話しいたします。
◎遺言の書き方について
公正証書遺言は費用はかかるものの、公証役場で作成してもらうため、法律に定められた有効な要件や形式について安心できます。
一方で、自筆証書遺言は費用がかからず簡単である一方、要件や形式を充たしたものを作成することに注意を払わなくてはなりません。不備があったために、自筆証書遺言が無効になってしまう事例も多くあります。
無効になった場合、自分の遺志が実行されない事態につながってしまいます。
自筆証書遺言の作成を検討されている方は方式をしっかりと理解しておくことが大切です。
まず、遺言の内容・日付・遺言者の署名の全てが自書である必要があります。
パソコンで作成したものや代筆してもらったもの、音声やビデオの映像での遺言は、効力は認められません。
次に、日付は作成日を明記し、署名は戸籍通りの姓名を記載して、印を押します。
書き間違いの修正や内容の追加は無効と判断される可能性がありますので、間違いのないように書き切りましょう。
遺言書は相続時の余計なもめごとを避ける目的があります。
あいまいな表現にせず、不動産は登記簿謄本通りに正確に、土地であれば所在地・地番・地目・地籍まで詳細に、預貯金は金融機関の支店名・預金の種類・口座番号まで、などと誤解の余地がない記載を心がけましょう。
遺言書で遺言執行者を指定しておくとさらに円滑に遺産分配が行われることでしょう。
◎遺言の作成にかかる費用について
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
このうち、自筆証書遺言につきましては自分自身で作成しますので特に費用はかかりませんが、公正証書遺言・秘密証書遺言につきましては、遺言書を公正証書にして公証役場で作成してもらいますので費用がかかります。
公正証書作成時の公証役場の手数料は、次のように定められています。
目的の価格が、
100万円までは5000円、100~200万円は7000円、200~500万円は11000円、500~1000万円は17000円、1000~3000万円は23000円、3000~5000万円は29000円、5000万~1億円は43000円1~3億円は5000万円ごとにさらに13000円加算、3~10億円は5000万円ごとにさらに11000円加算、10億円を超得る場合は5000万円ごとにさらに8000円加算、となります。
価額を算定することができない場合は500万円とみなして計算されます。
相続・遺贈額合計が1億円に満たないときは、上記金額に11000円を加算します。
なお、公証人が出張して公正証書を作成する場合には、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の数万円の日当と旅費も負担することになります。
正本又は謄本の用紙代として1枚あたり250円がかかります。
遺言書についてどの専門家に相談するかお困りの方へ
遺言書に関する手続きにつきましては、専門的で煩雑なものもあります。
そのため、よくわからずに不安だというお気持ちの方もいらっしゃるでしょう。
遺言書に関してお困りの際は、遺言書に詳しい専門家に相談すれば安心して作成・遺言に沿った相続の手続きを行うことができます。
遺言書の相談ができる専門家には、主に司法書士・弁護士・税理士・行政書士といった士業があります。
それぞれの特徴についてみていきましょう。
○司法書士
遺言書における遺産に不動産が絡む場合には、不動産をきちんと特定することが大切です。
このような場合には、登記申請の代理権を持っている司法書士に相談や依頼をするとよいでしょう。
○弁護士
紛争を解決するための代理権をもっているのは弁護士です。
遺言の内容によっては親族間に争いが生じることが予想される場合もあります。その様な場合に、法的視点から争いが起きない、起きにくいように的確な助言をする弁護士は、円滑に手続きを進める手助けになることでしょう。
○税理士
税理士は名前の通り税金の専門家で、相続問題に関連する専門家の中でも、税務申告に関する代理権を唯一持っています。
遺産総額が相続税の基礎控除を明らかに超え、相続税についても考慮が必要な場合の様に、遺言書に関連して税金の相談があれば税理士に訊いてみるとよいでしょう。
○行政書士
遺言書の作成に最も多く関わっているのは、実は行政書士ではないでしょうか。他の士業と比べて費用を抑えられることも特長です。
◎遺言書に関する相談は当事務所まで
遺言書に関しましては専門的なことも多いですので、いきなりどの専門家に依頼するかということやどのように動けばよいかということを決めるのは難しいという方もいらっしゃることでしょう。
そのような場合は是非たかの司法書士事務所の無料相談をご利用ください。
些細なことでもいつでも相談できる司法書士事務所でありたいと考えていますので、ご相談は全て無料でさせていただいております。
手続きの依頼をいただかない限りは料金をいただきません。
また、事前にご連絡いただきましたら、平日の夜間や土日祝日の対応も可能です。
実際に手続きを安心して始められるまで何度でもご相談をお受けいたします。
遺言書に関しまして何かご不明な点や心配されていることがございましたら、是非たかの司法書士事務所までご連絡ください。