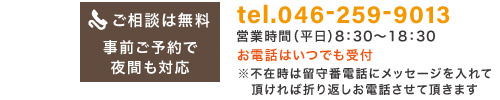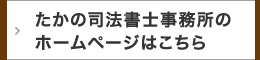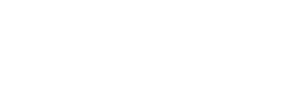Archive for the ‘コラム’ Category
遺言書の「検認」について、一連の手続きをご説明します
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります(詳しくは別記事にて紹介しております)。
このうち、自筆証書遺言・秘密証書遺言につきましては、家庭裁判所の「検認」が必要になります。
◎検認とは
遺言書の検認とは、遺言書を発見した人や保管場所を聞いていた人が家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人や受遺者の立会いのもとで、遺言書を確認する手続きを指します。
遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐためになされています。この手続きにおいては遺言内容の有効・無効は判断されません。
◎検認をしなければ
相続の各種手続きでは、検認済みの遺言書を提出しないと手続きを進めてもらえません。
なお、封印された自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の前に開封すると5万円以下の過料という罰則が存在します。ただし、この場合に遺言書が無効となることはありません。
◎検認手続きの流れは
遺言書が見つかって検認を申請する場合には、検認申立書の他、遺言者の出生から死亡までの除籍謄本、改製原戸籍謄本の全て、法定相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子およびその代襲者で死亡している方がいる場合はその方の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本・改製原戸籍謄本、といった書類を集めて、家庭裁判所に提出します。
なお、相続人が不存在の場合・遺言者の配偶者のみの場合・相続人が遺言者の兄弟姉妹(第三順位相続人)の場合は、遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本・改製原戸籍謄本、遺言者の直系尊属の死亡の記載のある除籍謄本・改製原戸籍謄本、 遺言者の兄弟姉妹で既に死亡している方の出生時から死亡時までのすべての除籍謄本・改製原戸籍謄本なども別に必要になります。
もし申立前に入手が不可能な戸籍などがある場合は,申立後に追加提出しても問題ありません。
申立ての費用として、遺言書1通につき収入印紙800円と相続人への通知用の郵便切手の代金がかかります。
提出書類に不備がなければ、2~3週間程で家庭裁判所から相続人全員の住所へ、遺言書を検認する旨と遺言書検認期日についての案内が郵送されます。
遺言書検認期日に申立人は遺言書原本・申立人の印鑑など指示されたものを持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きをします。
申立人がいれば他の法定相続人が出廷しなくても検認手続きをすることが可能です。裁判所にて封筒を開封し,遺言書を検認します。
遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので,検認済証明書の申請を行います。遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。
その後、検認証明付きの遺言書を使って、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などの相続手続きを行なっていくことなります。
以上、遺言書の検認についてお話ししました。
遺言を書かれる方、受け取る方、どちらにとっても大切な手段です。ご不明な点がございましたら、無料相談を承りますので、是非ご連絡ください。
遺産相続手続きの主な流れについてご紹介します
相続の手続きと言われてもなかなか想像するのは難しいかと思います。
まして、大切な方を亡くされてご心痛の時に冷静にお考えになるのは大変なことでしょう。
そこで今回は、是非とも押さえておきたい相続の手続(遺産に関するもの)と注意すべきことについてご紹介いたします。
被相続人がお亡くなりになった時点で相続は始まります。ただ、葬儀が終わってすぐに遺産相続の手続きをできる方はほとんどいないでしょう。だいたい四十九日法要を終えたあたりから動かれる方が多いです。
ただし、相続放棄が必要な場合(負債が多い場合)は、3カ月以内という期間があるため、早めに動く必要も出てきます。
遺産相続については、まずは遺言書の存在を確認します。遺言書があればその内容に従って手続きをする必要があるためです。遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3つの方法があり、公正証書遺言はすぐに内容を見ることができますが、封印された自筆証書遺言と秘密証書遺言については家庭裁判所での検認まで開封してはいけませんので注意しましょう。
次に、遺産を確認します。被相続人名義の不動産(自宅土地建物、賃貸用アパートなど)、預貯金、株、車などなど。預貯金などは、金融機関へ相続が開始した旨の連絡を行うと口座が凍結されます。
並行して、準確定申告を行います。申告手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から四カ月以内が期限となります。相続人が複数いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出します。この申告書は、亡くなった方の住所地にある税務署に提出します。
また、公共料金などの名義や、支払方法の変更の必要があれば、早めに行いましょう。
遺産相続のどの手続きでも必ず求められるのが、戸籍謄本などの提出です。誰が相続人になるか確認するためです。確認しないまま手続きを終えた後に実はもう一人相続人がいることが分かるという様な事になると、その相続人から訴えられかねません。
この相続人の調査は、被相続人が生まれた時から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍を全て取り寄せて確認することになります。
遺言書が無い場合、遺産が確定したら、相続人全員で遺産の分割を協議して、遺産分割協議書を作成します。その遺産分割協議書と戸籍謄本などをもって、相続財産の名義変更や預貯金の払い戻しなどを行います。
なお、遺産が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告および納税を行います。この相続税の申告は、相続開始から十か月以内にする必要があります。
以上、主な相続の手続きの方法と、その際に注意すべきことについてご紹介しました。
相続のことで親族同士がもめないようにしっかりと手順を踏みつつ期限に間に合うように進めていきましょう。
相続の相談先をお悩みの方へ各相談先をご紹介:無料相談承ります
相続について専門家に相談したいとお考えの時、どこに相談するべきかわからない方も多くいらっしゃるでしょう。
相続の相談先としてよく挙げられるのは、税理士・弁護士・司法書士・行政書士です。
誰に相談するかを決める参考にしていただくために、今回はそれぞれの特徴をご紹介します。
○税理士
税理士は、名前の通り税金の専門家で、相続問題に関連する専門家の中でも、税務申告に関する代理権を唯一持っています。
・相続税を節税するために、効果的な生前贈与の方法の相談
・遺産分割をするにあたっての、分割方法による相続税額の試算
・相続税の申告や準確定申告の依頼
などなど
相続税の計算や申告手続きを正確にしてもらえ、かつ節税の対策に関しての助言も受けられる可能性があるため、遺産総額が基礎控除額を明らかに超える場合には、税理士に相談・依頼するのが良いでしょう。
○弁護士
弁護士とは、あらゆる法律問題を取り扱うことができる法律の専門家です。
全ての裁判所における代理権を持っていて、当事者の代理人として交渉をすることも可能です。
当事者間に争いがある場合、代理人となって紛争解決に向けた交渉や訴訟などを行えるのは弁護士だけです。
・相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない。相手の顔も見たくないので第三者に代理人になってもらいたい。あるいは調停や訴訟にしたい。
・遺言の受遺者に対して遺留分減殺請求をしたい
などなど
弁護士は、法的な観点からささまざまなトラブルの解決にあたっていますので、遺産の相続に関する問題でも、トラブルを予測してそれを未然に防ぐための助言を得ることを期待できます。
家族以外の者に遺言を遺したい場合、他の相続人と揉め事になった場合、遺産の中に借金がある場合、遺留分減殺請求をしたい場合、といった紛争が予測される内容の相談は弁護士にするとよいでしょう。
○司法書士
司法書士は、登記・供託の代理・裁判所に提出する書類の作成提出などを行います。
相続によって不動産の所有者が移転したときには、所有権移転登記を行う必要がありますが、登記の専門家である司法書士は、登記申請の代理権を持っています。
家庭裁判所での、遺言書の検認や相続放棄申述などの書類作成提出をすることが可能です。
・不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記(団体信用生命保険で住宅ローンが完済された場合)
・遺産分割協議書の作成
・遺言書の作成
・遺言書の検認申立書、相続放棄申述書など家庭裁判所の手続の書類作成提出
などなど
その他にも、遺産管理人として依頼頂くことで、不動産以外の預貯金や株式などの相続手続きも行えます。
○行政書士
行政書士とは代理で必要な書面作成をしてくれる専門家です。
・相続人調査
・遺言書の作成
・遺産分割協議書作成
・車や株式の名義変更手続きといったことを依頼できます。
などなど
他士業に依頼するよりも安いことがありますので、費用と相談の上で細かい手続きを依頼するのもよいかもしれません。
◎無料相談は当事務所まで
相続に関しましては、専門的なことも多いため、いきなりどの専門家に依頼するかということを決めるのは難しい、という方が実際ほとんどです。そのため、当事務所では相談はいつでも無料で行っていますので、ぜひご利用下さい。
たかの司法書士事務所は、神奈川県全域におきまして、相続の手続きを承っております。
些細なことでもいつでも相談できる司法書士事務所でありたいと考えていますので、ご相談は全て無料でさせていただいております。
手続きの依頼をいただかない限りは料金をいただきません。
事前にご連絡いただきましたら、平日の夜間や土日祝日の対応も可能です。
相続に関しまして何かご不明な点や心配されていることがございましたら、お気軽にご連絡ください。
相続の登記に関連したお話:流れ・費用・期限について
相続の登記について、気になる、あるいはよくわからないという方もいらっしゃることでしょう。
今回は、登記に関して、流れ・費用・期限の四つの観点からお話しいたします。
◎相続の登記の流れ
相続が発生したらまず遺言書があるかどうかの確認が必要です。有効な遺言書があれば、遺言書の内容に従って名義変更登記をすることになります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には家庭裁判所での検認が必要になります。
遺言書がない場合は、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などの書類を集めて、相続関係説明図(家系図)を作成し、誰が相続人であるか、その全員を確定させます。
その後、誰がどの財産をどれだけ相続するのかを相続人全員で相談する遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して協議内容を明確にします。
この一連の相続の流れの最後にするのが「登記」です。管轄の法務局において不動産の名義の変更を行います。
◎登記にかかる費用
一連の手続きでかかる費用としては、戸籍謄本などの取得費、登記事項証明書の取得費などに加えて、登記を申請する際に法務局に納める登録免許税があります。
登記申請を専門家である司法書士に依頼をした場合には、司法書士に支払う報酬も用意する必要があります。
登録免許税は登記の申請時に支払うもので、固定資産評価額の0.4%を法務局に納めることになります。固定資産税評価額が土地建物あわせて2,000万円であれば、8万円になります。
登記事項証明書は、土地や建物の面積、現在の所有者や担保権者などが載った証明書のことで、法務局で取得することができます。これは、一通につき600円かかります。
◎相続登記の期限
相続登記につきましては、法律上の期限は決められていません。
相続登記をせずに放置することによる罰則はありませんが、不動産を売却する様な場合、必ず相続登記を経てからでないとできませんので、その時になって慌ててしまうという事もしばしばあります。
登記は、相続した不動産が誰のものであるかを事前に明確にしておく大切な手続きです。
期限がない分、忘れてしまいやすい手続きですので、早めに完了されることをお勧めいたします。
相続を放棄するという選択、必要な手続きと注意点について紹介します
相続が開始した場合,相続人は、
①被相続人(亡くなられた方)の土地の所有権等の権利や、借金等の義務をすべて受け継ぐ
②被相続人の権利や義務を一切受け継がない
③相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ、という三通りの選択ができます。
この二つ目の方法が「相続放棄」です。今回はこの相続放棄についていくつかの観点からご紹介します。
◎相続放棄はどのような場合に利用されているのか
相続の対象者が、遺産の相続を拒否する相続放棄を選択する場合の多くは、遺産が赤字である場合です。借金や莫大なローンといった負債が残っていて、財産額よりも大きい場合は、相続放棄によってその返済リスクから逃れることができます。
しかし、相続放棄が選ばれるのはこのよう場合だけではありません。相続放棄は理由を問わずできますので、たとえ遺産がプラスであっても、「争族」に一切関わりたくないという事で相続放棄する場合もあります。また、唯一の遺産が田舎の山林で売るにも売れず引き継ぎたくないという事で相続放棄する場合もあります。
また、まれにですが、家族で経営している事業を継いでもらうにあたって、資金を跡継ぎに集中させるために、他の相続人が相続放棄をするという場合もあります。
◎相続放棄に関して注意しておきたいこと
相続放棄は、基本的に相続開始後三か月以内に行う必要がありますが、亡くなられた方の資産や負債の存在をしばらく知らなかったということも考えられます。
そのような場合につきましては、相続開始後から三か月以上経過していても相続放棄が認められますので、知っていると安心です。
また、相続開始前に相続放棄の手続きはできません。
注意が必要なのは、相続放棄をしたとしても、相続財産管理人に財産管理を引き渡すまで、その財産がむやみに失われたりしないよう管理する義務はなくならず、負い続けるという点です。
◎相続放棄の手続きの方法と必要なものは
相続放棄の申述に必要な書類は、
①相続放棄の申述書
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
③被相続人の死亡の記載のある除籍謄本
④申述人の戸籍謄本 などです。
申述人が代襲相続人である孫の場合は、さらに被代襲者の死亡記載のある戸籍謄本が必要になり、申述人が被相続人の親の場合は、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要になります。
申述人が兄弟姉妹の場合は、追加で被相続人の親の死亡記載のある戸籍謄本が必要になります。
提出先は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄している家庭裁判所で、窓口または郵送で提出します。申述の費用としては、収入印紙が800円、切手代として500円程度かかります。
遺言書の作成時に気をつけたい、遺言が無効となる4つの事例
高齢社会の到来に伴い、遺言を書かれる方も増えています。ただ、遺言書に触れたことがないという人が大半のはずですので、書き方や形式、書く内容すらも何から書けばいいのか、と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。
そのような方に向けて、今回は遺言書が無効になってしまいがちな4つの事例をご紹介したいと思います。
1.パソコンやワープロで書かれている
自筆証書遺言を残そうとお考えの方は、署名だけでなく、遺言内容も全文が自筆(後から消すことができない筆記用具による)でないと遺言書として認められません。
パソコンで作成したものに署名と捺印があったとしても、遺言書としては認められないため注意してください。
2. 押印がない
押印も1と同様に必須です。署名か押印どちらかがあれば良いと考えがちですが、どちらも必須で必要ですのでお気をつけください。
3. 日付の記載がない、特定できない
また、その遺言をいつ書いたかも必ず記載してください。もちろん日付の記載も自筆である必要があります。
また、「2017年8月某日」などと、特定の日付がわからない書き方をした場合には無効となってしまうため注意してください。
4. 2人以上の共同で書かれた遺言書
いくら親密なパートナーといえど、2人で協力して書いたものは自筆証書遺言にはなりません。
基本的に、1人の手によって最初から最後まで書かれている遺言書のみが自筆証書遺言として有効です。夫婦で作成する場合は、それぞれ1通ずつ書く必要があります。
いかがでしょうか。
今回、失敗しがちな4つの事例をご紹介しました。これ以外にも遺言を書くときに気にしなければいけないことがあります。
もし不安を感じる方は、ご気軽にたかの司法書士事務所までご相談ください。
不動産の相続登記をしていないため困る場合
「親が残した不動産や土地を相続したいが、その際に必要な手続きがわからない。」という方や、「相続の手続きが面倒臭い。」という方がいらっしゃると思います。
しかし、だからと言って手続きを放っておくと、困ったことが後から出てくる可能性もあります。
そのような事態に陥らないためにも、今回は、相続登記を放置していたがための困ったことを少しご紹介します。
■不動産を売却したくてもできない
「親が所有していた土地建物を売却しよう。」
ご両親ともに亡くなり、自分も兄弟姉妹も持ち家に住んでいるため、ずっと誰も住まないまま放置していたが、建物の劣化も進んできたので売却したいという場合が、最近増えてきています。
土地建物を売却するには、必ず相続登記を行う必要があります。相続登記を経なければ売却はできません。
ご両親が亡くなった時であれば相続人で遺産分割協議がすぐできたはずなのですが、放置している間に、相続人である兄弟姉妹の一人と音信不通になったり、相続人の一人がその後亡くなり、その相続人が協議に応じないといった事情が生じてなかなか売却に至らないという事も実際にあります。
■遺産分割協議のタイミングを逃し、話がこじれる
財産や現金の配分というのは、比較的すぐに話をするものです。不動産は簡単に切って分けることができないため、なんとなく後回しにしてしまい、いざ協議をしようとしたときに、売りたい売りたくないなど、実はそれぞれの考え方が違って、揉め事が起こってしまうケースもあります。
遺産については、一部の財産だけをとりあえず分けるのではなく、最初に全てについて話し合って分ける方が断然お勧めです。
■余計な手間や時間がかかる
長年経ってから相続登記を行うと、役所の書類の保存期間の関係で取れない書類がでてきたり、法定相続人が増えてしまったりなど、余計な手間がかかることが多くあります。
いかがでしょうか。
相続登記には特に期限がないため後回しにしてしまいがちですが、このように、相続登記の手続きをしておかないと、後からトラブルや困ったことが続々と起こってしまう可能性があります。
もし、お困りのことがありましたら、たかの司法書士事務所まで、お気軽にご連絡ください。
相続の登記を自分で行う際に必要な手続きをご紹介します
相続の手続きを行う際に、年金など役所の手続き、銀行預金などの手続き、不動産の名義変更などにつて、できる限りは自分で行いたいとお考えの方もいらっしゃいます。
そこで今回は、相続登記をご自身で行う際の一連の流れをご紹介します。
■調査と相談
やはり、最初はインターネットでの検索や相続登記の本を読むことから始める方が多くいらっしゃいます。
しかし、特にインターネットは情報が多すぎて、これらに載っている情報の中でもどれが本当に自分に必要なのかわからないという方も多く、実際に法務局に行って相談をされる様です。
■被相続人と相続人全ての戸籍謄本を収集
まずは、相続にまつわる人全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を集めます。誰が相続人かを特定するため、相続に関するどの手続きでも必要になります。
近くの市役所で全て揃えば良いのですが、地方の実家にいた頃の改製原戸籍謄本を郵送で取り寄せるという場合には、申請書をダウンロードして小為替と返信封筒を入れて郵送するなど、これが結構面倒な作業となります。
■遺産分割協議書を作成
次に、相続人間の協議で不動産を誰が相続するかを決定し、遺産分割協議書として書面を作って、相続人全員で実印を押印し、印鑑証明書を付けて登記申請時に添付する必要があります(ただし、遺言書があれば遺産分割協議書ではなく遺言書を添付します)。
なお、相続人間で揉めてしまい協議がなかなかできない様な場合は、家庭裁判所の調停を利用したり、法定相続分で全員の共有で登記をするという事になってきます。
■固定資産評価証明書を取得して登記申請
上に述べた書類を完成させたのち、相続登記の際に納めなければいけない税金(登録免許税)を計算するため、固定資産税評価証明書という書類も登記申請の際に添付します(ただしこの扱いは法務局によって異なります)。固定資産税評価証明書は、市役所の資産税課で取得できます。
登録免許税額は、相続登記については、固定資産税評価額の0.4%です。
登記申請書を作成して、不動産を管轄している法務局へ赴き、今までに集めた書類と登録免許税分の現金を提出します。
かなり大雑把ではありますが、このような流れで登記申請を行います。
いかがでしたか。
役所あいての手続きのため、平日に限られ、お仕事をされている方はなかなか手間取ってしまう事も多いようです。
このような手続きを任せたいとお考えの方は、たかの司法書士事務所にお問い合わせください。
遺言書は司法書士や行政書士など専門家に相談
遺言書を書こうと考えだして、いざ書こうとなっても、何から始めたらいいのか、どういう風に書いたらいいのか分からないという方も多いと思います。
そのような方々におすすめしたいのが、司法書士や行政書士など専門家に相談することです。
・遺言書の書き方には決まりがある
遺言書の書き方は自由ではありません。民法で厳格にその方法が定められています。
何も調べずに遺言書を書いてしまうと、その遺言書が無効になってしまうこともあります。
しかし、自分で書き方を調べながら書くのは、いろいろな箇所で疑問や不安が沸き起こり、結構手間のかかることです。
司法書士や行政書士など専門家に相談すれば、遺言者の考えを正確に実現させるための書き方をお伝えすることができます。
・遺言書の文案作成もしてもらえる
自筆証書遺言書は遺言者自身が書かなければなりません。専門家に相談したとしても、それは変わりません。
しかし、専門家に文案を作成してもらうことはできます。
できた文案を一言一句書き写せば、問題なく遺言書を完成させることができます。
・遺言書の保管も依頼できる
遺言書が完成しても、保管場所をどうするかという問題が残っています。
受遺者(もらう人)に託しておくのが一番確実なのですが、自分が亡くなるまでは身内に見せたくないという場合、机の引き出しにしまっておく人もいるでしょうし、誰にもわからないような場所に保管しておく人も多いと思います。
しかし、亡くなった後に遺言書が見つからない事態になってしまっては本末転倒です。
その様な場合に、第三者である司法書士や行政書士など専門家に、遺言書の保管を託すのも一つの方法です。
・遺言執行の依頼もできる!
特に受遺者が相続人以外の方の場合、遺言執行者を定めておかないと、本来の相続人の印鑑が必要になるなど面倒な手続きになってしまう場合もあります。
受遺者の方を遺言執行者にすることができますが、受遺者の方に手続きの負担をかけるのも申し訳ないという方もよくいらっしゃいます。
そのような場合、司法書士や行政書士など専門家に遺言執行まで依頼することもできます。
専門家であれば、遺言書の内容を確実に実現させられます。
遺言書を書くことは人生で何度もありませんので、詳しい知識を持っている方はほとんどいらっしゃいません。
その知識を持っていて、確実に遺言者の考えを実現できるのは、司法書士や行政書士などの専門家です。自分で調べるのは手間がかかる、面倒な手続きを全て任せたいという方は、ぜひご相談ください。
遺言の作成方法-正しい自筆証書遺言の書き方-
「自分が子孫に残せるものは何かな」とお考えの方。遺産相続にあたっては、その多少に関わらず、親族の間に遺恨を残すこともあります。そのような場合、遺言書が遺されていれば防げたであろうと感じる事も多くあります。
もし、事前の準備次第でそのようなことを防げるのであれば、それに越したことはありません。
そのためにも、今回は遺言書の中でも最も手軽に作成できる「自筆証書遺言書の書き方」をご紹介します。これを参考に、自らの遺産や遺言について考えてみてください。
■正しさを担保する6つのステップ
自筆証書遺言書を作成する場合、有効に認められるために5つほどの確認すべきことがあります。
1.遺言の内容、日付、署名など全てを自筆すること
たとえ本人の意思が反映されているといっても、他者代筆やパソコンなどで作成されたものは有効な自筆証書とは認められません。音声やビデオについても同様です。
2.日付を明記する
2017年某日や、7月、などと特定の日が分からない日付の書き方はNGです。
また、日付を表すスタンプもNGです。日付も自筆である必要があります。
3.署名と押印をする
自分のフルネームを署名した後、押印して完了です。押印が無いと無効です。
押印は認印でも構いませんが、自ら作成した証明としては実印の方が好ましいと思います。
4.加除訂正に注意
書き間違い、書いた内容に付け足したいという場合、加除訂正方法が民法で厳格に定められていますので、全て書き直されることをお勧めいたします。
5.不動産や預金口座など、遺産は具体的に記載する
相続財産を特定できない曖昧な表現を使うと、場合によっては効力が認められない事も生じえます。またご子息たちも困ってしまいます。
なお特定せずに、「全ての財産」をAに、とかAとBに半分ずつといった記載でも構いません。
いかがでしょうか。
この記事を参考に、今後の自分の将来設計について考えてみてください。
ご不明の点などあれば、いつでもたかの司法書士事務所までお問合せ下さい。