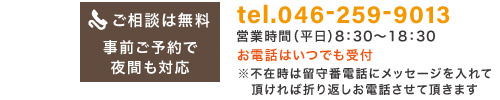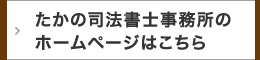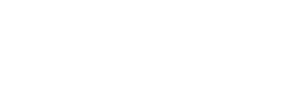Archive for the ‘コラム’ Category
遺産相続の手続きについての知っておきたい基礎知識
「ご両親がなくなり、葬儀を終えたけれども急な出来事だったため、遺産相続についての知識が全くない」
「自分の家庭があるため仕事を休めず、時間をかけずに遺産相続について調べたい」
とお考えの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は遺産相続について考える初歩の段階として、少なくともこれだけは知っておきたいという遺産相続の手続きの基礎知識についてお話します。
◇遺産相続の基礎知識
まず初めに、遺産相続については様々な事柄が法律(民法)で定められていることを知っておいて下さい。
亡くなった人の財産をどのように受け継ぐか、誰がどのような割合で受け継ぐのか、話し合いで受け継ぎ方が決まらない場合はどのように手続きを進めるのかなど、様々な事柄が民法で定められています。
そのため、民法に明らかに反する方法で手続きをしても、それは無効なものとされます。例えば相続人の一部だけで遺産分割をしても、それは無効とされます。
◇遺産相続の基礎語彙
遺産相続につき民法では、亡くなった人のことを「被相続人」と呼び、その財産を相続する親族を「相続人」と呼びます。誰が相続人となるかについても、民法で決められています。
親よりも子が先に亡くなっていた場合に、孫が相続人になる場合があります。その孫を「代襲相続人」といいます。その他、普段は耳にしない言葉がでてきますので、預金の相続手続きの書類など、初めての方には理解しにくいものである事が多いかと思います。
またよく耳にする「相続税」は、被相続人の財産を引き継いだ際にかかる税金のことをいいます。
遺産総額が相続税の控除額を超える場合、課税対象となり、納税をする必要があるので注意しましょう。
◇遺産相続での対象となる財産
遺産相続の際に受け継がれる財産はプラスになるものだけとは限りません。
借金や借金の保証人まで受け継いでしまいます。
ここでは、どのようなものが相続の対象となるのか確認しましょう。
・プラスの財産
現金、預貯金、有価証券、不動産(家、土地)、車、バイク、貴金属、家財道具、骨董品や美術品など。
・マイナスの財産
借金、連帯保証債務、未納税、未払い医療費など。
上記の財産を受け取ることや、借金の支払いなどを拒否するにはすべて法律上での手続き(相続手続き、相続放棄手続きなど)が必要になります。
いかがでしょうか。
遺産相続の際の基礎知識についておわかりいただけましたか?
法律上の手続きとなるとわからないことが多く出てくると思われます。
自分だけで調べることには時間も労力も使いますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
なるべく気軽に相談できるように、いつでも相談料無料にしていますので、たかの司法書士事務所までご連絡ください。
遺言書を作りたい、でも、誰に相談するのがいい?
「遺言書についてもっと知りたい」「自分だけでは不安だから、法律の専門家の話を聞きたい」
遺言書を書く機会はそうありません。いざ書こうとしても、「どう書けばいいのかわからず不安」という人は多いと思います。そこで、専門家の話を聞きたいと思うのではないでしょうか。しかし、専門家にも弁護士、司法書士、行政書士の3つがあり、どこに相談すべきか困っている人もいるはずです。そこで、今回は専門家ごとの特徴についてそれぞれ見ていきます。遺言書の相談をする参考にしてください。
・遺言書を書くのは必ず本人
最初に知っておいて頂きたいことは、「遺言書を書くのは必ず遺言者本人」ということです。自筆証書遺言はもちろん、公正証書遺言も、遺言者本人が述べた内容に従って公証人が作成します。専門家の仕事は遺言者の希望を聞き出し、適切な遺言書のお膳立てをすることです。遺言書を完成させるのは遺言者本人でなければいけません。依頼すればすべてやってくれるというわけではないので、ご注意ください。
・弁護士の特徴
弁護士は紛争解決の専門家です。遺産を巡って相続人間に紛争が生じることがほぼ確実である様な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。法的紛争について当事者の代理人となって交渉していくのが弁護士で、裁判などを通じた紛争解決の経験やノウハウを積んでいます。将来の紛争を最小限にとどめるための遺言書や、遺言書自体が紛争の種になるであろう場合など、弁護士の経験・ノウハウが役立つかと思います。
・司法書士の特徴
司法書士は不動産登記の専門家です。相続の多くの場合に不動産が関わるため、不動産以外の財産も含めて、相続手続の専門家として多くの経験を積んでいます。裁判沙汰など紛争が生じる様な事は無いものの、遺産を巡って揉めることのない様に遺言書を遺しておきたい、相続人の中に長年音信不通の者がいる場合や子供がいない場合など遺言書を作っておいた方が良い、といった多くの場面でお役立ちできると思います。
・行政書士の特徴
行政書士は法的文書作成の専門家です。不動産登記以外の事では、司法書士と同様に、相続手続の専門家としてご相談頂けます。
・相続税がかかる場合には税理士も
税金の専門家は税理士です。上記3つのどの専門家に相談する場合でも、遺産総額が相続税の基礎控除を超えて、それなりの相続税額が発生するであろう場合には、税理士に試算してもらいながら遺言内容を考える事も重要です。遺産の分配の仕方で相続税額も変わります。まず自分の知っている税理士に相談してから、あるいは相談した弁護士・司法書士・行政書士に紹介してもらいながら、遺言内容を決めていく様になるでしょう。
今回は遺言書の相談を頼める専門家をご説明しました。弁護士・司法書士・行政書士のいずれについてもそうですが、各事務所でそれぞれ専門分野もあります。また当然ながら人柄は十人十色で異なりますし、相性が合う合わないもあるでしょう。相談をする際はまず複数の専門家にあたってみるのも良いかと思います。
何が違う?エンディングノート・遺言書・遺書3つの違いを解説
「最近、エンディングノートっていう言葉をよく耳にする」
「エンディングノートって書店でも見かけるけど、遺言書と何が違うの?」
こうした疑問を抱いている方は多いのではないでしょうか。「終活」がメディアで取り沙汰されるようになり、注目を集めています。そんな「終活」の一環として行われるのが、自分の気持ちや考えなど、遺志をまとめておくという作業です。その際に使われるのが、遺書や遺言書というものでしたが、最近登場したのが「エンディングノート」です。しかし、「3つの違いがわからない」や「どうやって使い分ければいいの?」と悩む方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は「遺書」「遺言書」「エンディングノート」の違いをご説明します。
・法的な効力を持つのが「遺言書」
「遺言書」の目的は主に自分の財産を遺族がどう分けたり処分したりするべきかを伝えるものです。いわば、遺産相続に関する指示書だとお考え下さい。遺言書には、遺言の内容を実現する法的効力が認められ、遺族や遺言執行者は遺言に従って遺産を分配・処分しなければなりません。法的効力を与えるため、民法によって形式が明確に規定されており、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。民法の形式に従わない遺言書は無効になります。
・自分の意思を伝えるのが「遺書」
遺言書とは異なり、「遺書」は私的な文書となります。遺書の目的は自分の気持ちや思いをまわりに伝えるのが目的だからです。家族や友人といった親しい人に向けて書かれることが多く、形式にも特に決まりはありません。パソコンで作ったものや映像でも構いません。なお、やはり自筆で紙に書くのが一般的だと思いますが、財産に関して遺言書の形式を備えていれば、遺言書としての法的効力も認められます。
・自分の死後知ってほしい情報を残すのが「エンディングノート」
「エンディングノート」とは自分がいなくなった後、まわりの人間に知ってもらいたい情報を載せておくものです。例えば、お墓や葬儀の方法、形見分けの指示など書いておく内容は多岐にわたります。実際に、何十ページにもわたるノートも珍しくありません。また、医療方法や延命治療の希望を書くこともできます。つまり、意思表示ができなくなった時への備えとしての役割も持っています。遺族はエンディングノートを見れば、故人の遺志がわかるので助かることでしょう。ただし、法的拘束力はなく、必ずしもノートの内容に従う必要はありません。
今回は「遺書」「遺言書」「エンディングノート」の違いについてご説明しました。簡単にまとめるとこのようになります。
遺産の相続方法を指示する法的文書である「遺言書」
自分の意思や思いを伝えるのが「遺書」
自分の死後、遺族に知ってもらいたい情報を書くのが「エンディングノート」
ぜひご参照ください。
無効にならない遺言書の書き方
「遺言書って自分で書いていいの?」
「遺言書を書きたいけれど、どうやって書けばいいの?」
この様に、遺言書をいざ書こうとしてもどうすれいいのかわからない、そんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。遺言者本人が書く遺言書は自筆証書遺言と呼ばれます。専門家に依頼もする必要もないので、多く利用されています。しかし、要件や形式に不備があり、せっかく書いた自筆証書遺言が無効になることもあります。そこで今回は無効にならない遺言書の書き方をご説明します。
・必ず遺言者の自筆にする
自筆証書遺言を作成する際は、必ず遺言者本人が書く必要があります。代筆してもらうことはできないので注意してください。また、必ず書面として遺言書を作る必要があり、音声や映像のデータは遺言書としては認められないので、気を付けましょう。そして、遺言書は手書き(自筆)である必要があります。パソコンで作成したり、ワードソフトで作られたりしたものは無効となります。身体的に自筆が困難な場合は、他の形式の、公正証書遺言などで作成することになります。
・日付・署名は明記する
作成日がはっきりとわからない遺言書は無効となります。何年何月何日に遺言書を書いたのかしっかりと明記しておきましょう。また、同様に遺言者の名前もしっかりと明記しておいてください。ペンネームや下の名だけなどではなく、戸籍通りの氏名を書いて下さい。
・押印を忘れずに
署名と同様に重要なのが、押印です。何故なら、押印のない遺言書は無効となるからです。押印の種類に特に決まりはありませんので、認印でかまいません。ただ、確かに本人が書いたという証拠として、一般的には実印を用いるのが理想とされています。
・内容を訂正する場合は書き直すほうが無難
場合によっては、遺言書の内容を書き直したいということもあるかもしれません。また、内容を追加したいこともあるでしょう。このように遺言書を訂正したり、追加したりするには法律が定めた方法に従う必要があります。もし違う方法で訂正をしてしまうと、その遺言書は無効になりかねません。訂正をしたい場合は一から書き直すことをお勧めします。
今回は利用の多い遺言書である、自筆証書遺言の書き方についてご紹介しました。これを参考に遺言書を書いてみて下さい。また、どうしても不安だという方はお気軽にご相談下さい。
遺言書ってどんなもの?終活に必要な遺言書の3種類の形式について
人生は終わりがあるものです。「自分の死を悲しんでくれる人に迷惑をかけたくない。」近年そう感じる方が増えているのででしょうか、就活ならぬ「終活」という言葉がテレビでもよく取り上げられています。「健康なうちにいずれ来る人生の終わりに対して準備をしておきたい」、「相続の際に家族にトラブルが起きてほしくない」など様々な思いで「終活」をする方がいらっしゃると思います。そこで必要になるのが遺言書です。自分の遺産相続を円滑に行ってもらうために欠かせないのが遺言書で、「終活の一環でとりあえず書いてみようかな」とお考えの方はたくさんいらっしゃいます。そこで今回はそんな遺言書の3種類の形式について簡単にご説明します。
・遺言書には3種類ある
一口に遺言書と言っても、大きく3種類に分けることができます。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言 の3つです。遺言者はこの3つのどれかを選んで、相続人に遺言を残すこととなります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が自分一人で書く遺言書を指します。紙と、ペンそして印鑑があればいつでも作成可能で、法律の専門家に依頼する必要もないので費用も掛かりません。ただ、全文を自筆で書かないといけないため、身体的に書くことが難しい場合には他の種類の遺言によらざるを得ない事になります。また、一番手軽な自筆証書遺言ですが、素人だけで書いてしまうと内容の不備などが起きる可能性がどうしてもあります。不備がある遺言書は、その部分が無効、あるいは全体が無効になってしまします。なお、自筆証書遺言を手続きで使うためには、遺言者本人が死亡後に、後述の家庭裁判所での検認手続きを経なければなりません。
・公正証書遺言
確実に遺言書を残すために利用されるのがこの公正証書遺言です。遺言の内容を公証人に伝え、公証人に作成してもらいます。このメリットは、公証人が法的ルールに則って作成するため後に無効とされる様な危険がまず無い点、仮に遺言書を失くしてしまっても原本が公証役場に保管されている点です。また、家庭裁判所の検認手続きは必要なく、すぐに相続手続きに使うことができます。
この公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要で、公証人への手数料等がかかります。
・秘密遺言書
遺言内容を他人に知らせたくない。こんな思いを遺言者が抱えることもあるでしょう。このようなときに利用されるのが秘密証書遺言です。自分で作って封印した遺言書を、公証人と証人2人の面前でさらに公証役場で封印します。内容を公証人がチェックすることは無いため、自筆証書遺言と同様に不備による無効の危険があります。内容を身内に知られたくない場合であれば、証人を全くの第三者にして公正証書遺言にする方が安全かと思います。
・遺言書の検認
公正証書遺言書以外の遺言書は本人の死後、家庭裁判所で相続人とともに開封され、存在を公的に認められる必要があります。この手続きを検認と言います。相続の各種手続きでは、検認手続きを経た遺言書が必要になります。また、封印された自筆証書遺言書を検認手続きを行う前に開封すると過料を科されてしまいます。
今回は遺言書の種類について簡単にまとめました。ぜひご参考にしてください。次回は遺言書の書き方についてご説明します。
有効な遺言と無効な遺言
「こんな遺言書絶対認めない!」
このようなセリフを、ドラマの中で一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
これはテレビの中の話だけではありません。身内が亡くなった後に遺言書が見つかったけれど「書かれていることを本当に実行していいのか。」「不公平な内容で身内と揉めそう。」と悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。
そこで今回は遺言書の有効・無効についてご紹介します。
■遺言で書かれていて有効なもの。
遺言に書いて法的効力をもつ事項は民法等で決められています。それは大きく分けて3つあり、「財産」「身分」「執行」です。
まずは財産ですが、遺言書があれば法律に従った割合で相続することはなく、亡くなった人の意志に沿った財産の分配が可能になります。ただし、後に述べる遺留分に注意が必要です。
なお相続人以外の人でも受け取り可能で、遺贈といいます。
次に「身分」に関してですが、遺言で婚外子の認知を行うなどができます。
最後に「執行」ですが、きちんと遺言書の内容を執行してもらう人が選ばれていないと、遺言書通りに財産が分配されないかもしれません。また、相続人以外への遺贈の場合は執行者を選んでいないと面倒な手続きが必要になってしまいます。
■遺言書で無効になるもの
上記の内容以外の事が書かれた遺言は、例えば「家族みな仲良く暮らすこと」という記載は法的な効力は持ちませんが、遺言自体がそれで無効になるということはありません。他の記載事項は有効です。
無効に近い事項として、よく当事者で揉める原因の一つになるが「遺留分」です。
この「遺留分」に関しては、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人は、侵害された分をよこせと請求することができます(遺留分減殺請求といいます)。
次に無効になる(自筆証書)遺言の形式です。遺言が執行される時にはすでに遺言した本人は他界していて、本当に本人の意思で書かれたのか確認できないため、民法で決まっている形式で書かれているという事が一番重要視されます。
動画や音声で残された遺言や、パソコンで作成した遺言は無効になってしまいます。
また、うっかり抜けているかもしれない「日付」もなくてはダメです。
また、亡くなった本人のみが全文・日付・氏名を書いた遺言書でなければいけません。
■遺言書についてよくある疑問
まず、苗字が変わっている場合でも、旧姓で書いたものを書き直す必要はありません。戸籍を見れば分かるからです。
また、亡くなった方が悩んで何度も書き直したものが何枚も見つかる場合があります。その場合、日付の新しいものが有効になります。
そして亡くなった方の意思で書かれたものでなく、強要されて書かれたものは無効です。
最後に遺言書を見せる人を特定することはできません。
遺言書が有効・無効についてざっくりですがお分かりいただけたでしょうか。本サイトの遺言についての各ページに、より詳しく記載していますので、ご覧いただければと思います。
遺言書の言葉一つ一つに亡くなった方の思いが託されています。揉め事を少しでも起こさないためにもぜひ、遺産相続の際は参考にしてみてください。
死亡後にまずやらないといけない役所関係の手続き
大事なご家族が亡くなるとそのショックはとても大きいです。しかし、ご家族が亡くなった後に残された方がやらなければいけないことは沢山あります。その時になって何をしていいのかわからない、ということがないように今から相続手続きのやり方を少しでも知っておきましょう。
■死亡届の提出
死亡診断書が病院から発行されます。これは後々の手続きで必要な書類で、入手したらコピーをとっておきましょう。この書類はその方が亡くなったことを医学的かつ法律的に証明するものなので、これがないと死亡の証明ができず、火葬や埋葬、公共料金の支払い、年金受給、税金関係で混乱が生じてしまうこともあります。病院によって金額は異なりますが、大体5000円ほどかかります。入手したら印鑑と共に、死亡した地域か本籍地の市区町村役場まで提出しに行きましょう。
■年金受給停止の手続き
亡くなられた方が年金を受給していらっしゃった場合は、決められた日数以内に年金証書、死亡診断書、戸籍謄本などを用意して年金受給停止の手続きを行わなければいけません。受給停止の申請期間は、厚生年金の場合は死後10日以内、国民年金の場合は死後14日以内となっています。また、年金の給付は二か月ごとなので、一部未払いの場合もあります。その際は、その分の給付の申請を行ってください。
■介護保険の資格喪失届
亡くなられた方が介護保険の被保険者であった場合は、その資格喪失届けを市区町村に提出する必要があります。もし要介護認定を受けていたのなら、14日以内に介護被保険者証も返還しましょう。亡くなられた方が65歳以上かつ未納保険料がある場合は、相続人に請求されます。逆に保険料を納めすぎの場合には相続人に還付されるということも、合わせて覚えておきましょう。
■住民票の抹消届
これは死亡届の提出によって自動的に処理されるので、特別な手続きは必要ありません。しかし、亡くなられた方が世帯主であった場合には、世帯主変更届の提出が必要です。また、住民票の除票(住民登録が抹消された住民票)は、その後の手続きで必要になってくるので故人の住民基本台帳カードと届出人の身分証明書を用意して、取得しておくようにしてください。
■世帯主の変更届
亡くなられた方が世帯主であった場合、死後14日以内にこの手続きを行う必要があります。しかし、残された世帯員が一人、もしくは残された世帯員が15歳未満の子供とその親権者の2人である場合には必要ありません。
まずは上記の手続きを経たうえで、財産の相続手続きなどへ入っていくことになります。相続の手続きへ入る頃にはある程度落ち着いていると思いますが、上記はまだ混乱の最中で行わなければならないため、今のうちにおおまかな流れを掴んで頂ければと思います。
相続放棄をするときの注意点
「亡くなった親父の借金が発覚した...」銀行系カード等がスピード審査で作れるなど、お金を借りやすくなった時代。
親が亡くなった後の相続放棄の可能性も他人ごとではなくなってきました。
「もし親に多額の借金があったらどうしよう。」と不安な方、またはすでに、相続放棄を申請しようと考えている方も中にはおられるでしょう。
そこで、今回は相続放棄を行うときの注意点とやるべきことをご紹介します。
■相続放棄をしようと決断する前に。
相続放棄を行うと、借金だけでなく、自分にとってプラスになること、つまり、継ぎたい遺産も放棄しなければいけません。
基本的に全てを引き継ぐか全てを放棄するかのいずれかの選択になります。ここが安易に相続放棄をしてはいけないといわれている所以です。
受け継ぐものの中に株や自宅が含まれている場合など、きちんとプラスとマイナスを考慮して、相続放棄の手続きを始めなければいけません。
また、相続放棄の申請期間は被相続人が亡くなった次の日から原則3か月以内となっています。
この期間内に家庭裁判所に申出書を提出しなければなりません。
■相続放棄を行うともう後戻りできない。
借金や遺産相続の争い、相続の際に必要な様々な手続きに関与しなくてよくなるところが相続放棄のいいところですが、デメリットも大きいです。
それは後から相続放棄の取り消しができないということです。詐欺や脅迫などの事情が無い限り取り消しはできません。
後から自分にとって大きな利益となる遺産が発覚しても相続することができないので、慎重に決断しなければなりません。
■相続放棄の前に相続財産に何があるのかきちんと確認。
相続放棄をするべきかどうか決めるには、自分が相続するかもしれない財産には何があるのかしっかりと把握する必要があります。
確認する内容は、預金はいくらか、不動産の有無、証券の有無、借金があるかどうかなどです。
これらの確認のため遺品の整理はある程度徹底した方がよいでしょう。タンスの引き出しの隅に知らなかった銀行通帳があるかもしれません。
現物がなくても郵便物や電話帳、日記などの記録から、何らかの取引が分かる場合もありますので、隈なく目を通すようにしてください。
今回は相続放棄を行う際の注意点とやるべきことを理解いただけたでしょうか。
手続きの詳細については、本サイトの相続放棄の各ページでより詳細に記載していますので、参考にして下さい。
遺言で揉めないために押さえておきたい5つのポイント
遺産相続で揉めないために遺言書を残そうかとお考えの方もいらっしゃるかと思います。しかし、その遺言書、ただ書けばいいというわけではないのです。今回は、そんな遺言書(自筆証書遺言)を書くときに気を付けたい5つのポイントについてお話しいたします。
■曖昧な表現は避ける
遺言書に記載されている表現が曖昧なために、実際にトラブルに発展してしまうこともあります。特に日付はきちんと明確に記載するようにしないと遺言書自体が無効になってしまうので、注意してください。具体的には「平成○○年○月吉日」が無効とされた裁判例があり、「平成○○年○月○日」と記載するようにしてください。 そして内容自体も、誰に、何を、どれだけ相続させるのか、明確に分かる表現を心掛けてください。特に「何を」では、不動産は登記簿を見ながら、預金は通帳を見ながら、株式や証券は証券会社の資料を見ながら記載することをお勧めします。例えば、「海老名の家は長男に」と記載している場合、海老名市内に自宅のほか貸家も持っていると、自宅のみか両方なのか分からず手続きができないといったことも起こりえます。
■相続財産の場所も記載しておく
現金や預金、不動産、株式や有価証券のほか、宝石類、美術品、骨董品なども相続財産になります。これらの財産分与の仕方について記載しても、その所在が分からないと分けられません。自宅内に全部保管してあれば良いのですが、身内の誰かや、信頼できる第三者に預けているなど、財産の所在を被相続人のみが知っている場合、忘れずにその保管場所も記載しておきましょう。「財産目録」という財産一覧表のようなものを別に作成しておくのもいいでしょう。
■遺言書の保管場所
遺言書は残された方たちにとって、非常に大きな意味のあるものです。したがって、一度作成したらそれが必要になるときまで、厳重に保管しておかなければなりません。特に自筆証書遺言はご自身で気軽に作成できる分、保管もご自身でしっかり行わなければいけません。ただ逆に、あまり厳重にしすぎると相続人の誰も見つけられず、みな遺言書は無いと思って手続きを進めてしまう事もありえます。後記の遺言執行者や、信頼できる者に託しておくか、自分の金庫などに保管する場合は亡き後に所在が分かる様にほのめかしておくなどが必要です。 なお、銀行の貸金庫は注意が必要です。遺言書で遺言執行者を定めていれば、遺言執行者が貸金庫を開けることができますが、そのためには遺言書を提示することが必要です。ところが、その遺言書が貸金庫の中にあるとそもそも開けなければ提示できません。その場合は、相続人全員の同意書で開けることになりますが、協力しない相続人や連絡のつかない相続人がいると貸金庫を開けることができず、せっかく書いた遺言書を取り出すことができなくなります。
■遺言執行者を決めておく
遺言内容をそのとおりに実行するのが「遺言執行者」です。相続人の中の1人を遺言執行者にすることが多いのですが、遺言書の内容で相続人間で揉める可能性がある場合には、この役割を家族以外の信頼できる方に頼んで、遺言書に明確に記載しておく方が良いかと思います。遺言書を作成するときに協力してもらった弁護士、司法書士、行政書士などに遺言執行者を依頼する方も多くいらっしゃいます。
■遺言書の内容変更は遺言書で行う
遺言書の内容を後日変えたいという場合もあるかと思います。そんな時は必ず遺言の方式で行わなければなりません。内容すべてを撤回したいのであれば、遺言書自体を破棄すればそれで大丈夫です。一部を変更したい場合は、変更したい内容だけ別で新しく遺言書を作成します。訂正印を押して書き直すのではないことに注意してください。
以上のポイントに気を付けて遺言書を作成してください。
法務局による法定相続情報証明制度
6月から、法務局による法定相続情報証明制度が開始されました。
相続登記のほか、銀行や証券会社での相続手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍が必要になります。だいたい5通以上、多い方だと10通以上になる方もいらっしゃいます。
通常は各1通取得して、各種手続きに原本を提出してコピーをとってもらい、原本は返してもらって次の手続きで使う、を繰り返します。郵送でやり取りする場合には、原本が返ってくるまで次の手続きができない事になります。
法定相続情報証明制度は、法務局に、相続関係が記載された図と一緒に除籍等を提出すると、その図に記載された相続関係で間違えないという証明をしてくれるものです。相続関係図を必要な手続きの数だけ発行してもい、その証明図を提出すれば、原本を返してもらってという手間が省け、また各種手続きを一度に平行してできます。
法務局への申請は、相続人本人で行うか、司法書士などの一定の資格者に代理で行ってもらう事になります。
手続きの詳細については、いつでもお問い合わせ下さい。
Newer Entries »